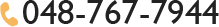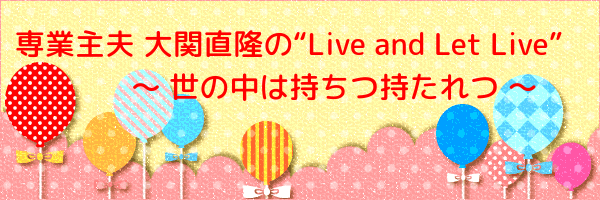【Q】
今春、今の会社に入社しました。これまで嫌なこともなく働きやすい職場だと思っていました。一緒に入社した男性は時々残業しているようですが、私は残業を強いられることもないし、少しの遅刻なら、やかましく言われることもありません。むしろ「具合でも悪いの?」と上司が声をかけてくれたりもします。ところが先日の忘年会でのこと。私のことを名指しで「あいつはなんでお酌に来ないんだ?」と上司が話している声が聞こえました。どうしようか迷っていたんですけど、よほどごまをすりたい人は別ですけれど、同期の男の子たちはほとんどお酌に行く様子もないので行かなかったんです。なんで私だけ?と思いました。それで親しくしている女子の先輩に聞いたんです。そうしたら、「女性の新入社員はあなただけなんだから行かなきゃダメよ」と言われました。これまでいい会社だと思っていたのに、いっぺんに気持ちが変わってしまいました。
【A】
忘年会シーズン、この悩み、結構皆、感じたことがありますよね。上司に「お酌」をしに行くかどうか・・・。この「お酌」という風習、文化は、どうも日本独特のものらしく、ヨーロッパやアメリカなどでは、パーティ参加者同士が注ぎ合うという習慣はないようです。プロのソムリエなどが、職業の中でも高い技術を誇って、今でも仕事として行っていますよね。この「お酌」という行為は、男性の専門職として存在する一方、歴史の中で、古今東西、男性が女性を「性」のしもべとして、宴会のときに侍らせる、そして、そのサービスとしてお酌をさせるというのがもうひとつの目的です。
ご相談の方は、女性先輩から言われた「女性新入社員だから」という言葉に、その性的役割を感じ、「いっぺんに気持ちが変わった」わけですよね。考えてみれば、今まで嫌なこともなく気持ちよく働いていられたのは、残業を強いられることがなかったのも、少しの遅刻なら許され、「具合でも悪いの?」と上司が声をかけてくれたのも、実は、「女性の新入社員」だったからということがわかりましたね。
そもそも、「お酌」という呼び名は、舞妓、芸妓、芸者、半玉、御酌さんたちのことをいう中のひとつの呼称で、それぞれに役割や年齢が違ってはいますが、男性にサービスをするということでは共通しています。元来、「芸」を売るということが本業で、芸者勤めをすることを「左褄(ひだりづま)を取る」とも言いますが、これは彼女たちには厳しいしきたりがあって、歩く時には必ず左手で、着物の褄(帯から下の裾までの併せ目部分のこと)をしっかり持って歩くようしつけられています。左手で褄を持つことで、着物のあわせ目から男性の手が入りにくくなり、「芸は売っても身体は売りません」という決意を表しています。
“とき”と“ところ”、時代がかわると共に、この厳しいしきたりも緩んできたり、彼女たちの職業の中身にも変化がでてきます。高額の値段でその身体を売る花魁(おいらん)の話は、今も映画や演劇、近松の文学の中にも残っています。そのような歴史の中で、「お酌する」という行為は、「女性が男性に媚びる行為」ととられるようになったのです。
その後、出世しようとする男性たちも、これを真似たようですね。
歴史から考えるとあなたが感じたように、「差別」、「女性蔑視」の風習だと私も思います。
「だから私はお酌はしない」(若き日の私同様)と決めてお酌をしないあなたを応援します。多少のいづらさを覚悟しなくてはなりませんが。(酒席には参加しないという選択肢もあります)
ただし、仕事で媚びへつらっての酒席は、もう日本文化の中からなくしていきたいものですね。
お酒は飲みたい人と飲みたいように飲む。仕事は女性でも男性でも、きちんと対等にこなす。女だからという甘えも自分に許さない。厳しいかな?それくらいなら、酒席でお酌をするほうがましですか?
私たち女性を抑圧するたくさんの歴史に抗(あらが)って生きてきた、たくさんの先輩たち。女性が男性化して、男性みたいに行動するのではなく、男性が女性に近づく努力をしてくれる社会を作りたいと切望してやみません。
第16回